本居宣長/小林秀雄
- 2016.08.16
- BLOG
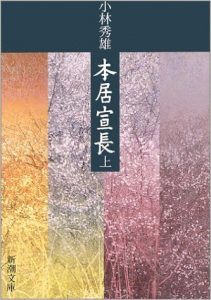
僕にとって小林秀雄という人は、批評家を超えて、本当に価値のあるものをきちんと分かっている人というか、この人が良いものだ、と言えば無批判に信じてしまうような存在(言う程著作を沢山読んではいませんが)であり、その人が10年以上かけて取組んだ本居宣長には本当に大切な何かがあるに違いない、との思いこみ?で買ってあったままでしたが、読むのは大変でしたがなるほど、大切な何かを垣間見られました。
読み終わってある程度理解できれば、こんな厚い本にクドクド書かなくても良いんじゃ?と感じますし著者も言ってますが、つまり、宣長が評価した源氏物語や古事記、というのを、その当時の心持ち、つまり文字や漢学などによる価値観の固定化をする前の、言霊を感じられた時代に自らを置いて感じる事でそこにある「もののあはれ」を感じなければいけない、という主張は、少しでも評論的な立場に立てば不可能な事であり、だからこそ宣長も随分批判もされて来たようで、その誤解も解きつつ宣長の信じる事を伝えるためにはこのクドクドしさが必要だったんだと思います。少し似たものとして「現象学」は人間は既に出来てしまっている社会の中で偏見という色眼鏡を透してものを見ざるを得ないけれど、その色眼鏡を外してどう見えるか?というのが現象学的態度だとザックリ説明してしまえば、文字も含めた社会が作るルールという色眼鏡がまだなくて、例えばこの花は桜だとも知らず、というか花という概念もない状況で桜を見た時に、「はぁ〜〜〜」と簡単のため息をつく、それが「あはれ」であり、漢字が入って来る前に音としての言葉しかなかった時には言葉や歌はそのあはれを伝えるものであり、言霊、という通りの生々しいものであったというのかな。もしかして、何故人工物は見飽きるけど自然のもの(大自然やそれこそムク材も)は見飽きないのはその生々しさを感じているからなのかも?
そこで思い出したのが以前読んで、僕はとても感銘を受けた「神々の沈黙」。そして宣長の言う源氏物語や古事記の世界は、もしかして「意識」がなかったと言えるのではないか?と。でもそれぞれ1000年、700年のころにまだ意識がなかったのか?と言われれば、島国だった日本ならそうだったんじゃないかと思います。「感じる、信じる」という右脳の働きが人間の動作を支配し、「考える、疑う」という今のような左脳の働きは漢字や中国の学問によってもたらされたのかもしれませんし、ヨーロッパや中国は大陸で常に異民族と戦って来たので意識の発生も早かったのではと。
また、意識の世界は「地図」に喩えられていた、と書いていましたが、つまり地図があれば全体を見渡して、目先の判断もできるのですが、地図とはつまり「色眼鏡」ですよね。ガイドブックを持った旅行のようなもので生々しい驚きは少なくとも減じるでしょう。そして意識以前の世界は、いきなりどこでもドア(古い?)で見知らぬ土地に放り出されたように、全てが生き生きと感じられ、それを表現するのが音としての言葉であり、古代の歌はそれを歓びをもって歌っていたようです。
ところで、小林秀雄さんは有名ですが骨董好きで、関連した文章なども読みましたが「国宝 大井戸茶碗 喜左衛門」って一番有名だと思いますが、そもそも朝鮮で日用品として作られたものだったそうです。でも、そこに何故「美」が在るのか?そして意識的に作った茶碗がこれを超えられないのか?という事にも同じ本質が存在しているようにも思いました。↓これですね
