ミースの建築と今考えてること
- 2025.08.17
- BLOG
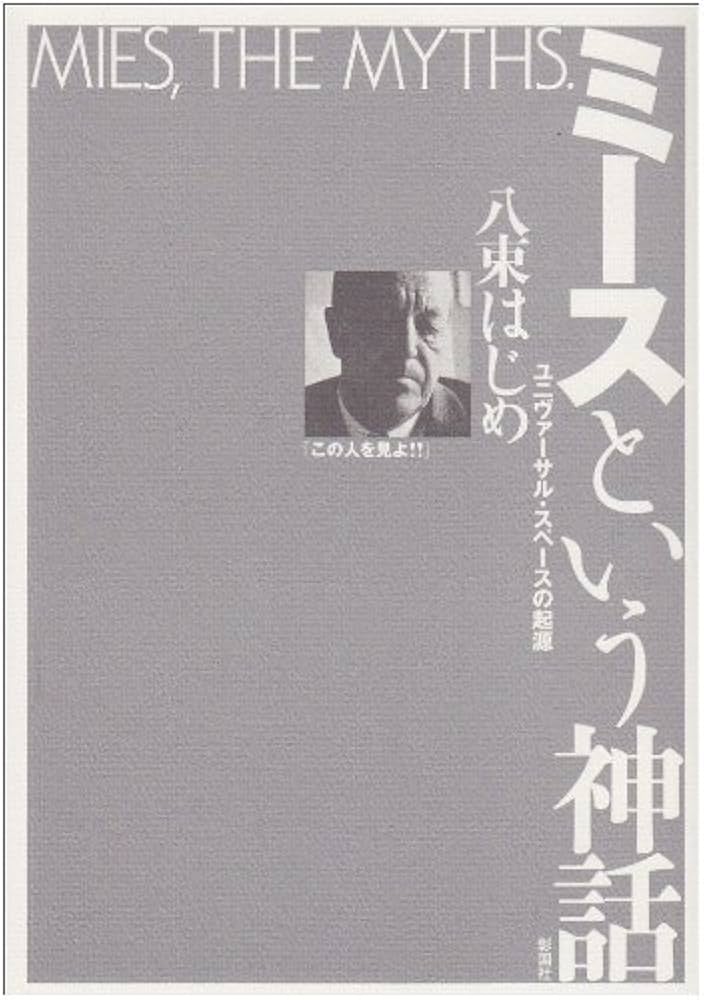
ずっと前に読んだ本だけどこの休みに時間があったのでミース再考しようと他数冊読み直した。
建築に限らないと思うけど自分で形を決める、というのは安易に考えれば安易だけど真剣に考えればキリがなく、キリがない探求の先にしか良い建築は現れない。
という意味でミースはコルビュジェやライトに比べると一般人には認識が浅いと思うけど僕らの世界では一番影響を与えているのだと思う。それも本人は一冊も本は残していないのに。かたやコルビュジェは文章/言葉や写真でとても大きな影響を与えた。でもミースと比較すると軽薄なのだ。
本書のタイトル「神話」というように建築の世界ではミースは体系立った言葉を残してくれなかったので勝手な想像が膨らんで神話化しているところがあるけど、出来るだけ本当のミースに迫ろう、という良書。
大事だと思ったのは、ミースは建築の「正しさ」を追求した「だけ」ということ。
人生の「正しさ」を追求する、とすると、枝葉末節の正しさを積み重ねれば到達できるか?いやむしろ枝葉末節は全て切り捨てないと本当の芯となる部分が見えてこないだろうのと同じで、ミースもだから、そのクライアント、や細かな与条件に寄り添ったような機能性や使い勝手を積み上げて設計することは全く「ない」。
結果、人の家でなく「神」の家のような建築となるのは必然だったのだろうけど、かといって使いにくくて訴訟されたわけでもなく、アメリカに渡ってからは作ったものが一般的にも評価されたからこそ多くの作品を残しているし、愛されている。
そして、美しい建築を目指そうなんて思ってないけど上記のスタンスだと結果当然美しくなる。また個別の要望や機能を盛り込んでいないから使いにくかったりしないのか?については30年、50年単位で考えたり所有者が変わったり、状況が変化するのが当然という前提では、むしろ目先の使い勝手に振り回されたプランや建築なんていうのは10年で価値が落ちると思った方が良いと思う。
自分のデザインモチーフなんぞ、語るべきではないのだけど、僕が近年フラットな天井で、屋根の構造材は隠してしまいつつ、竿縁なるものを使ったりしているのは、以前も書いたかもだけど、ミースが木造で作ったらどう考えただろう?というのを自分なりに考えてきた結果でもある。
ミースは小さな住宅では鉄骨の構造を現してデザインもしたけど大規模なものは耐火被覆が必要となり現すことができない。そして現れたのがマリオン。主構造ではないけど鉄骨の主構造のイメージを表出させる手法を発見した。そして外観も内部も至ってシンプルな箱型を目指しているのだけど、逆にいうと、そうではない形を使うというのは用途やデザインや、何らかを付け足していることなので、その付け足しはミースには決して許せなかったということ。言葉を変えると「恣意的」であることを許せなかった。
でも建築を作るって、要望や土地の形状や、社会的背景や、「恣意的」を避けてデザインするというのはとんでもなく困難なことだけど、でもそれを諦めて安易に作るから、すぐに価値のなくなる代物になるのだと思う。
さて明日から仕事だ。ミース先生目指して頑張ろう。