利休の茶/堀口捨己
- 2023.07.12
- BLOG
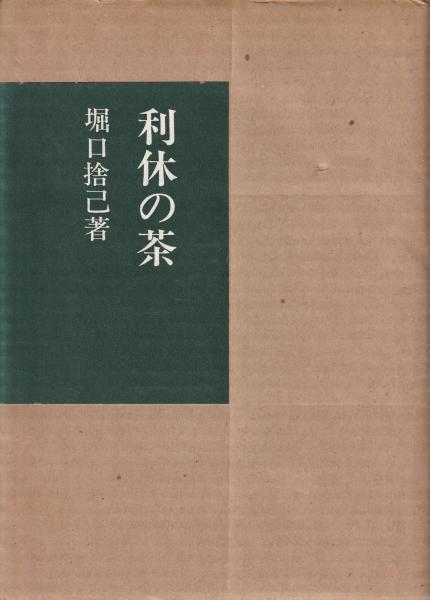
日本で木造を作っているならいつかちゃんと向き合わなければ、というところで。。
1951年に書かれ旧字体で厚い本だから読み流したところも多いけど、利休たちが作った「茶」の深さはずっしり伝わる。
堀口がこれらを書いたのは、もともと仲間と「読茶会」なるものを作り、コーヒー!を飲みながら文化としての茶の湯を語り合ったのがきっかけのようだけど、なぜ「読む」なのか?それは「茶を飲む」「茶を嗜む」と言えるような茶の心得や立派な茶道具の所持が無かったからだそう。でも裏には、形式化し大切な部分を知ろうとしないまま行われている事への違和感があったのだろう。
「利休の茶」と言っても茶の歴史はずっと古く、利休が大成したとは言え、有名なところでは珠光や紹鴎らの時代からの流れがあったからの事だし、「位高い主人が自らそこに出て、客のために茶を立てる」ようなことは「神や仏に仕えるが如き姿」と言うような、茶の湯の世界的にも珍しく、かつ重要な側面がその中で生まれていたことはより大切なことであろう。
それは、深い世界なので雑な書き方しかできないけど「侘び茶」であり、「正直に慎み深くおごらぬ様を侘びと言う」そうだ。それは室町時代〜戦国、安土桃山時代、という権力や絢爛さが溢れる時代のアンチとして生まれた面も大きいのだろう。
そしてそんな侘びの世界を実現するためと言えるのか、興味深く読んだのは、「床の間」はそこに飾られる掛け物の文字や絵と言うのはその作者がそこに同席しているような存在感の強さを持ってしまうため、茶の湯の世界と「調べ合わすための中性的な空間」として役に立ったのではないか?と言う部分。そして必然的に墨蹟のようなモノトーンで「余白」を持つようなものが選ばれてきた、と言う。
床の間はたまに設計させて頂いて来たけど、そういう本質的な面を知らないままだと、形式的に真似ざるを得ないし、極論してしまえば茶の湯を極めて亭主としてもてなせるような状況でなければ、形式的に真似た床の間などは不要だ、とも言えるかもしれない。
また本書では「利休の茶杓」「利休の炭」に半分以上を割いている。特に茶杓を竹で作るようになってから、素人でも(利休もたくさん作ったそう)自ら向き合い心を触れさせるような精神的な要素を内包することで茶の湯は500年という伝統を作ることができたのだろうし、楽茶碗は素人が直接作るものではないけど表現としての素人的なもの、として同じ役割を果たした、ようである。なるほど。COOL JAPANみたいな能天気なのは嫌いだけど、でもそれだけ洗練させ続けられた文化というのは我々人間の本質に間違いなく迫っているものだと思うので、もっと大事にしなければいけない。
そして「炭」については単に沸かすだけの道具を、客に見せ、演出するものとしての「炭手前」に昇華させたのが利休だ、というのだが、それは演出的ではなく、上記のように神や仏に仕える主人として客人をもてなす、道を極めた結果という事なのだろう。
なんてちょっと分かったような書き方になってしまうのが一番いけないのだろう。
近くに松韻亭があるのだし茶道を本格的にしてみるのも良いかも、とずっと思いつつ、やっぱり僕も「飲茶」でなく「読茶」の方が向いている。でも利休の茶の湯のように、自ら場を設え、主人となり、客人を深く精神的にもてなす、ということは他のやり方でも出来るはずなので、これからまだ先の長い人生で少しずつでも取り組めたら、と思う。