江戸時代日本の家
- 2012.02.08
- BLOG
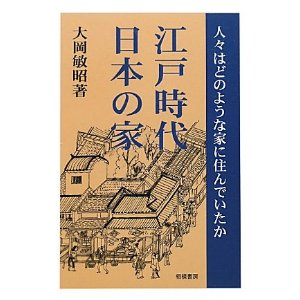
ちょっと地味ですが改めて読んでみたくなりまして。
だいたいどこかで聞いた様な話ですが、武士や農民等、階級それぞれの家の間取りが載っていて、とても大きなものではなく、最小限の生活だった部分が結局現代の住宅につながっている、というか残り得たということが分かり興味深かったです。
まずは城下町の武士は何より客を迎える場としての座敷を道路に向けるのが大前提で、基本的に方位とは全く無関係だったけれど、農家はそんなきっちりとした道路に囲まれている訳でもなく庭先の作業も多く南入りがほとんどだったようです。でも仏壇を置いたり行事のために結局必ず座敷はできたし、農民レベルでそんな接客空間があったというのはとても特別だった、と言えば確かにそうかもしれないですね。それに伴って、入口の土間を下手として一番奥の座敷を上手という空間の秩序が確立したようですが、上座下座って欧米人には信じられない習慣のようですが、彼らには絶対的な「神」という上(駄洒落みたい)という秩序がある代わりに日本には上下という秩序があるのだと言えば理解されるのかな?とふっと思ったので近々誰かに聞いてみます。
そこで思うのは、近代建築というのはそういう上下のような空間内のヒエラルキーを撤廃すべくあったと思うのですが、それでも絶対の神は以前として存在する社会が源流だったわけですが、日本のような八百万の神の社会や尚更現代なんて様々な価値が余りにも相対化し過ぎた世の中なんだから、逆に建築や住宅内には上下のような秩序が存在した方が良いのではないか?という自分がつくっているものへの我田引水的な推論ですw。
あと本書でも触れられている、住む、澄むは「じっとしている」という意味で同じ語源であり、「済む(気が済むとか)」も併せて考えると、落着くべきところに落着いている様子、という意味で同じ語源のようで、これも示唆に富むと思います。
住宅設計をするなら大切な知識だと思うのですが、この手の事は建築系大学ではほとんど教えられないのですよね(最近は多少変わったのかな?)